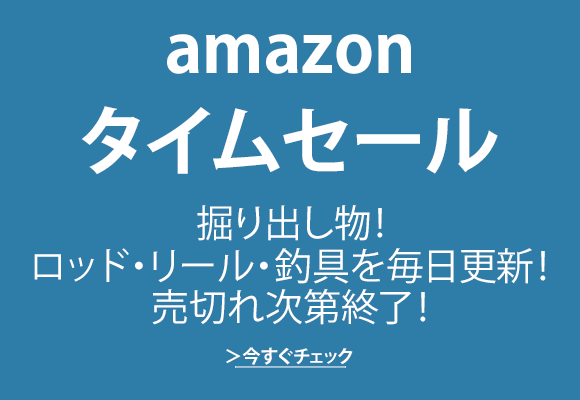タイの語源は、「タ」は「平たいこと」
「イ」は「魚(イオ)」
の意味で「平たい魚」という説や
「タイは大位かた呼び名で、コイは高位からきたもの、ともに海陸の魚をそれぞれ代表する王者」
と語呂合わせのような説。
「めでたい」魚という説もあります。
真鯛は古くから朝廷への貢ぎ物にされたり、
宗教儀式の供え物として欠かすことができない「縁起のよい魚」とされてきました。
また、タイは、日本書紀には赤女とあり、延喜式には平魚と書かれていたことから、
鯛も文字は平安朝の頃から用いられたと考えられています。
真鯛の養殖の歴史
1920年代には養殖池での飼育、繁殖の実験が行われ、50年代に種苗生産の実験が始まり、60年代には大量生産の技術が確立されました。
海面に浮かべた生簀養殖だけではなく、放流事業も盛んに行われてきた。
その結果関東でも春から真鯛の稚魚が浅場で見かけられる様になりました。
2023年加筆
この記事を書いたのが9年前
それから時は流れて時代はAI
話題のChatGPT先生にもマダイの語源と養殖の歴史について聞いてみました。
マダイの語源と養殖の歴史について
「マダイ」という言葉は、日本語の魚の名称であり、その語源についてはいくつかの説があります。
一つの説によれば、「マダイ」は「真」(ま)という字が使われるようになったのが起源とされています。これは、真鯛が古くから高級な魚として珍重されてきたことを表しています。
また、別の説では、マダイの語源は古代ギリシャ語の「pagros(パグロス)」に由来するとされています。この言葉が中国や日本に伝わり、音や意味が変化した結果、「マダイ」という呼び名が生まれたと考えられています。
養殖におけるマダイの歴史は古く、日本では約400年以上前から養殖が行われてきました。江戸時代の頃から、日本各地の浦や漁村において、マダイの養殖が営まれていました。
しかし、本格的な商業養殖が盛んになったのは、昭和時代後半からでした。特に、1970年代以降、養殖技術の進歩や水産業の発展に伴い、マダイの養殖はさらに拡大しました。
現在では、マダイの養殖は日本をはじめとするアジア諸国や地中海沿岸などで広く行われています。養殖によって供給されるマダイは、高い品質と食味の評価を受け、日本料理や寿司の一品として人気を博しています。
出典元『ChatGPT』
だそうです。
あわせて参考にしてみて下さい。